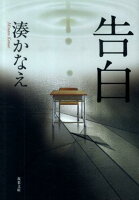特に用事もなかったのですが、今週有給を一日取りました。ところが、どうしたことか前日夜から寝つきが悪くどうしても眠れず、そういう時は読書をしようと午前2時ごろから手に取ったのが本作。まあ当然ですが余計に眠れなくなり、本作読了し、朝の7時に就寝しました。無駄な時間の使い方ですが、贅沢なひと時でありました。
以前ネットフリックスで映画を見て、インパクトがある作品だなあと感じていました。その後書籍で買ったのですが、本屋大賞受賞作というのは知りませんでした。
あらすじ(裏表示から)
「愛美は死にました。しかし事故ではありません。このクラスの生徒に殺されたのです」
わが子を校内で亡くした中学校の女性教師によるホームルームでの告白から、この物語は始まる。語り手が「級友」「犯人」「犯人の家族」 と次々と変わり、次第に事件の全体像が浮き彫りにされていく。衝撃的なラストを巡り物議をかもした、デビュー作にして、第六回本屋大賞受賞のベストセラーがついに文庫化!
ひとこと感想
語り手が入れ替わり、異なる切り口が提供されることで、広がりのある作品となっていると感じます。
5章だてで人の視点で語られるのですが、それぞれの視点はどれも真実らしく、でもちょっと嘘っぽくも感じるものでした。なお、その語り手は、教師(森口先生)、級友(委員長:美月)、母親(少年Bの母)、少年B(直樹)、少年A(修哉)。
読んでで気持ちよくないのが気持ちいい?
さて、湊氏の作品でよく言われるイヤミス、そしてゆがんだ母子関係。本作でもこれらのテーマはしっかりと組み込まれており、今回も気持ち悪いところが気持ちいい?感じでした笑
子供を殺害された森口先生の学年最後の日に語る教壇でのあいさつは怖かった。先生の冷静さを保ちつつ、せつせつと理知的に事件を振り返り誰が娘を殺したのかを語るのですが、語りがやはり普通じゃありません。どこかでネジが外れたかのような狂気を含んでいます。そもそも殺人について生徒の前で語るというのが普通ではありませんよね。映画では松たか子さんが教師役を熱演ならぬ冷演?されていました。
母子関係ということですと、犯人Aとその母親、犯人Bとその母親、どちらの関係も歪でありました。
犯人Bと母親の関係は、母親の価値観押し付けパターンでしょうか。理由の説明もなしに「○○はこういうものだ」みたいな断定的固定的な価値観を子供だけでなく周囲に押し付ける親。いわゆるモンペ的なタイプで、今でいうところのエンパシーとか共感力がないタイプ。こういう親が同居するところで引きこもりになり、次第に毒されていった少年Bは最終的に母子ともども崩壊。。。
犯人Aと母親の関係はどちらかというとA少年の一方的マザコン的な建付けに見えました。周囲に認められたい、なかでも、離婚して東京で働く母親に認知してほしい・褒められたいという自己顕示欲が起こしたのが今回の事件の発端となっているように思います。最終的に少年Aも理想の母親像が崩壊し物語が終了しますが、その後どうなったのかが少し気になるところです。
おわりに
ということで、すごい話でした。
小説も映画もどちらも面白かったと思います。ただ、巻末で中島哲也監督が語るように、映画と原作では少し構成が異なります。その点では名前は同じでも別な料理であると思います。どちらも特徴があり、美味しく頂くことができました。
学園もの、ミステリ、イヤミスなどを鑑賞したい方にはお勧めできる作品です。
評価 ☆☆☆☆
2022/10/26