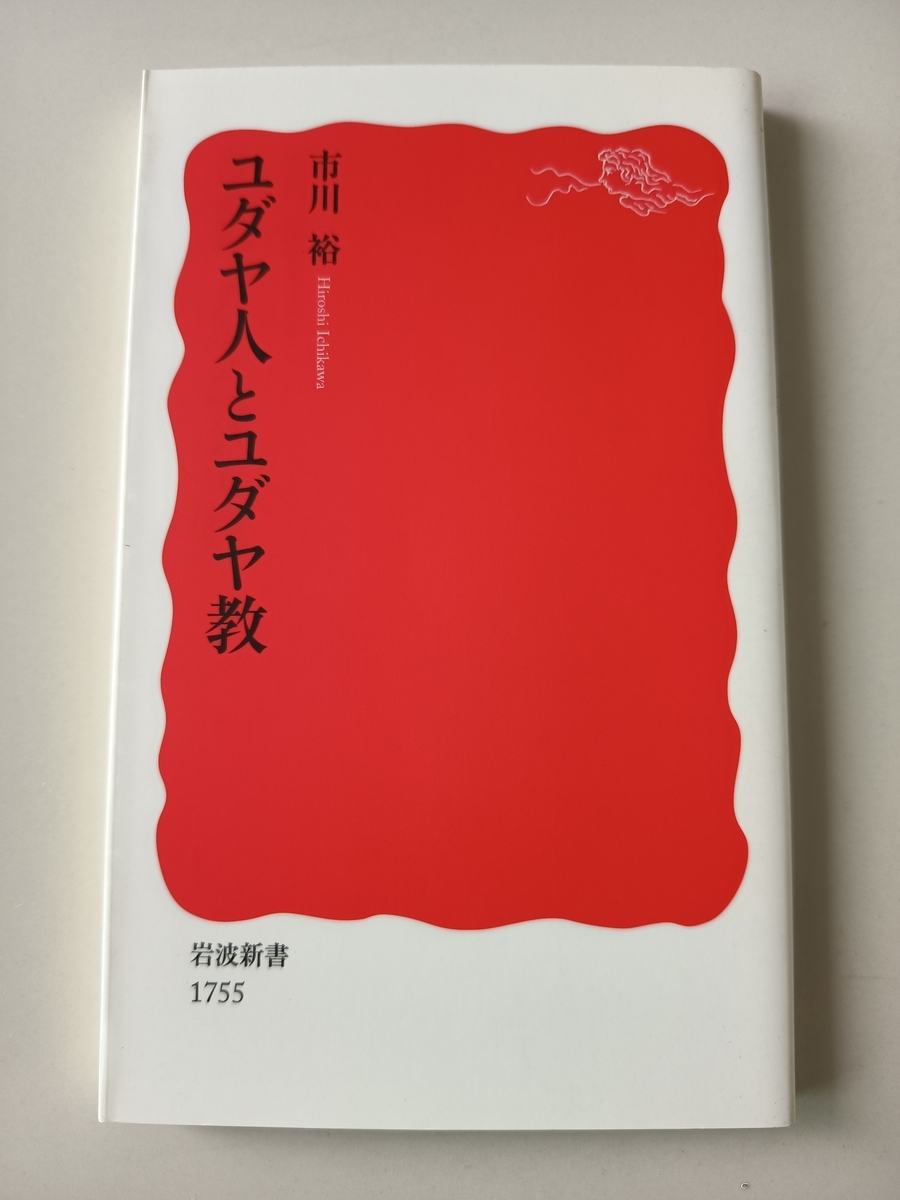皆さん、こんにちは。
ところで皆さん、ブログを書かれるときはパソコン派でしょうか、それともケータイ派でしょうか。
私はいらち気味でして、とにかくサクサクやりたいというのでパソコン派であります。ばちばちキーボードをたたいて、記事を作る。
ところが過日、ケータイも意外といいと気づきました。
一時帰国で飛行機に乗っていた時、持ち合わせていた本は既に読んでしまい、パソコンもない。ケータイにもオフラインでアクセスできる気になるコンテンツもない。で本の感想でも書いとくかとGメールで自分宛のメールを作成し下書きとして感想を書いていたのです。
で、まず気づいたのがフリック入力。一文字ワンタッチです。他方、ローマ字入力だとカナ一文字につきキー二回の入力。これはスピードはケータイに軍配が上がります。
そしてサジェスト入力。これにより大分文章がサクサク作れることに気付きました。PC(というかWORD)ですとサジェストしてくれませんし、打鍵ミスも多い。やはりスピードはケータイの方が早い。
そういうの総合的に考えるとケータイの方が時短かもしれない、と感じた週末であります。
ちなみに今調べてみたらWORDにもサジェスト機能みたいなの、あるそうですね。確かに会社のOutlookとかもスペルミスとか勝手に直してくれたりしますね。家のパソコンは日本国外で買ったため英語仕様のWORDのままでイマイチ使い勝手悪いまま使っており、改善できるのか不明なんです。やっぱり、ケータイでの記事作成に鞍替えしようかなあ…。
ということで本題に参ります。
選書の背景
部下が育ちません。
中途入社して三年目、期待とは未だ程遠いと言わざるを得ません。自分を棚に上げて言うのもなんですが。
で本作。過去にも読んだのですが、再読して何とか自分の指導力の足しにできないかを探ったものです。
自分に気付いてしまった
自分の気持ちの状態というのも多分にあるのですが、初めて読んだ時より響きませんでした。
なんというか自分が今、諦めモードになっています。育てる気になれない、諦め、スケーラビリティの放棄をしたい、自分でマクロを共通部品化して効率化を進める方が良い気がします。
不備を発見し語気が強くなる自分自身も嫌だし、何度言っても分からず、分かったかどうか問うているのに分かりましたと(自身なさげに I see, とかいう)答えることにも幻滅している。本当に分かっている?と覗き込むように問うと、分かりませんとか返事する。いや、それがだめなの(分かったふりをさせてしまう私がだめなのでしょうが)。
こういうとき、デキる上司ならば表現を変える、相手の立場にたつ、とか諸々手を打つのでしょう。
ただ、もう私出世もないだろうし、会社にも期待されていないし、それこそいつまで居るか分からないしとか考えると、やる気がでません。ひどい上司で申し訳ないのですが。
でも、人を育てるというのが重要であることは初めて部下をもったことで理解しました。次世代・後進を育成するというのは大事です。他方、こうした定量化しづらいタスクは評価もされづらく、だったら「流す」「しているふり」でもいいかなと考える邪な自分も居ます。
業務のレベル分け・図示
他方、再読して、思い出して、改めてやってみようということもありました。
例えば、従事している業務を5段階で図示しレベル分けすることなど。
これは言わばゴールの共有ですね。
レベル1から5まで明文化して、大体あなたはレベル3です、で私たちが目指すのはレベル5です。頑張ってください、みたいな会話ができるといいなと。
いいこと書いてくださいます。
ただ、魔法の質問・声かけはいくらか試してみたのですが、いまのところダメ。
おわりに
ということで部下育成術系の本の再読でした。
今回は余り響きませんでした。部下については何とかしたいとは思っているけど、もうダメでもいいやとも薄っすら思っています(我ながら酷い話です)。とすれば読むべきは自分のやる気を起こす本であったのかもしれません。
世の部下を持つ人たちがどうやってやる気を出しているのか知りたくなりました。ホントに皆さん、尊敬致します。お疲れ様でございます。
評価 ☆☆☆
2025/10/15









![総理の夫 [DVD] 総理の夫 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E5mNbDPTL._SL500_.jpg)